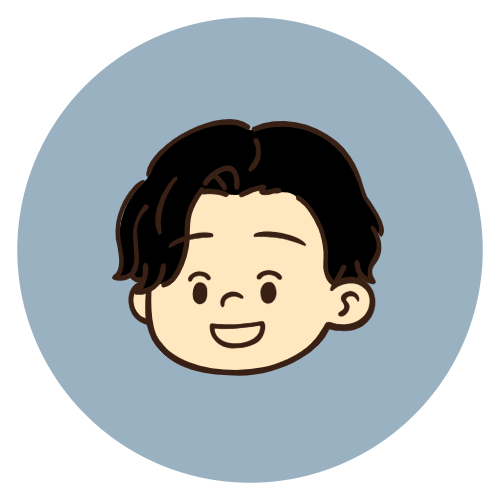奈良県橿原市にある巨岩「益田岩船」
奈良時代に作成されたと推測はされていますが、詳細を記した文献は残っておらず使用目的や制作者等が謎に包まれています
写真とともに詳しい内容をお伝えします
益田岩船までの道のり

小学校や子ども総合センターに続くカラーロードの道中に益田岩船への入り口があります
その道中には犬やウサギ等の可愛い絵が描かれているのですが、益田岩船も同じテイストで描かれています

こうみると本当に宇宙船のようですね。横に描かれている人も白いシルエットで宇宙服感があります

見上げると階段が。ここが入り口
結構きつそう

階段を登り切ると、林に到着。お茶休憩をしようと立ち止まると
「ぷ〜ん」
蚊がうぜえ!!
虫を払い除けるように手を扇ぐと、パシパシと蚊が当たる感触があり、蚊が一匹や二匹ではないことがわかる
虫除け対策は必須です

益田岩船の特徴
入り口から10分程進むと大きな岩が見えてきます。これが益田岩船か。めちゃくちゃデカい

近づくと格子縞模様に岩が区切られていることが確認でき、縦横と均一性があることから、明らかに人の手が加わっていることがわかる

岩を中心にグルリと一周してみる

看板によると益田岩船のサイズは、東西に約11m、南北に約8m、高さは約4.7m。重さは推定800トン
別角度に回り込んで岩を観察する。不時着した宇宙船のように見えます

上部には二つの方形の穴が空いている
間隔は約1.4mで2つとも横約1.6m、深さ1.3mとその大きさは等しいと看板に記されています
別角度の側面も縦方向の線に均一性があることが確認できる


この岩は花崗岩である。花崗岩はとても硬い素材で、加工に相当な技術が必要。ここまで滑らかに彫り上げるには相当な人手と技術者が携わっていたことが推測できます
また写真からも分かるように益田岩船は急斜面に位置している。沢山の人が集まって作業するには、急斜面上では明らかに非効率だし、せっかく加工した岩を傷付けずに動かす際の労力も相当な物だろう
急斜面に位置するこの場所で加工をしなければならない意味があるように思うが、その理由は明らかとなっていない
益田岩船が作成された目的は?
ここでは益田岩船の使用目的に関する幾つかの説と個人的見解を記入しています。
特定の説を事実であると主張するものではありません
ボケーとした奴が感想を記入しているだけなので、小学校低学年頃の子どもの作文を見るような
暖かな気持ちで見てくださいね
貯水池作成の記念碑説
江戸時代に刊行された『大和名所図鑑』には平安時代に造られた灌漑用の貯水池「益田池」の築造を記念して弘法大師・空海が建立した石碑の台石と紹介されています
早稲田大学図書館古典籍総合データベース 『大日本名所図会 第1輯 第3編 大和名所図会』(大正8年)https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/search.php?cndbn=大和名所図会
上部の穴は石碑を差し込むための穴ということでしょうか?
しかし、肝心の石碑は現存していないと言う。解説板にもこの説が記入されていますが、
何故、側面に模様が刻まれているのかよく分かりませんし、益田池の完成は825年と伝えられています
益田岩船の加工法から推測するに制作は7世紀(600年〜)ごろだと考えられているので、益田池の完成と制作年代が合わず、個人的にはあまり納得ができる説ではありません
古墳説
益田岩船から500mほど南東には牽牛子塚古墳があります
牽牛子塚古墳は巨石をくり抜いて造った2つの玄室を持つ特殊な古墳で、横口式石槨(せっかく)という形式です
この益田岩船はその石槨を建造しようとして途中で放棄された物。つまり、現存する牽牛子塚古墳の失敗作ではないかと言う説です
側面の模様は、石を古墳に使用するため整形しやすくするためのものだと考えられています
<参照>
橿原市公式HP
橿原探訪ナビ史跡 牽牛子塚古墳(明日香村)https://www.city.kashihara.nara.jp/kankou/own_sekaiisan/sekaiisan/kouseiisan/kengoshizuka.html
確かに、岩をよく観察すると裂け目があり、穴に貯まった雨水が流れ出している
これでは確かに古墳としての役割には適していない

ちなみに牽牛子塚古墳は花崗岩よりも軟質で加工しやすい「凝灰岩」が使用されている。花崗岩では上手く加工できなかった失敗を活かして、「凝灰岩」を使用したのだろうか
ただ、個人的な感想としては横穴に玄室を設ける形式の古墳なのに、なぜ縦の状態で穴を掘っているのか?加工をしやすいからなのかな??
それにしても、現在の形から横倒しにする手間がエゲつないように思うので腑には落ちない
ゾロアスター教徒のための拝火台説
これは松本清張『火の路』で唱えられている説です。この小説では「ペルシャ人が飛鳥京を訪れ、ゾロアスター教を伝えた」「益田岩船はペルシャ人が残した石造物」等と大胆な推理が展開されています
「そんなわけないだろ」とツッコミを入れたくなる話ではあるが、7世紀頃にインドを始め中東のペルシア一帯から多くの文化人や宗教家が来日していたことが日本書紀に記されています。ゾロアスター教はペルシア一帯で栄えた宗教です
加えて、
2016年10月に平城宮跡から、ペルシャ人とみられる「破斯(はし)清通」という役人の名前が書かれた8世紀中ごろの木簡が出土していたことが、奈良文化財研究所の調査で明らかになりました
平城宮にペルシャ人役人 – 名前記した木簡が出土/平城宮跡 8世紀中期 奈良新聞 2016年10月6日 http://www.nara-np.co.jp/news/20161006085811.html
したがって、「ゾロアスター教徒のための拝火台説」の可能性は0ではないように思います
実際、東大寺の二月堂で行われる「お水取り」も一説にはゾロアスター教を源流としていると言う説もあります
サライ 源流はなんと古代イランのゾロアスター教!奈良・東大寺二月堂「お水取り」の謎に迫る(2)https://serai.jp/tour/44963
以上3つの説を紹介しました。その他、天文台説や火葬墳墓説等もあるようです
アクセス
住所:〒634-0051 奈良県橿原市白橿町8丁目20−1
駐車場:なし
営業時間:年中無休
駐在する管理者はいません
まとめ
益田岩船
想像する以上に大きな岩で迫力がありました
何でこんな物が造られたのか・・・?形が本当に謎!
マイナースポットではありますが、歴史浪漫溢れる、ミステリアスで魅力的な場所でした
史跡好きや古代好きの方はもちろん、どんな方でも楽しめる場所だと思います!
以上です
最後までご覧いただき、ありがとうございました!!