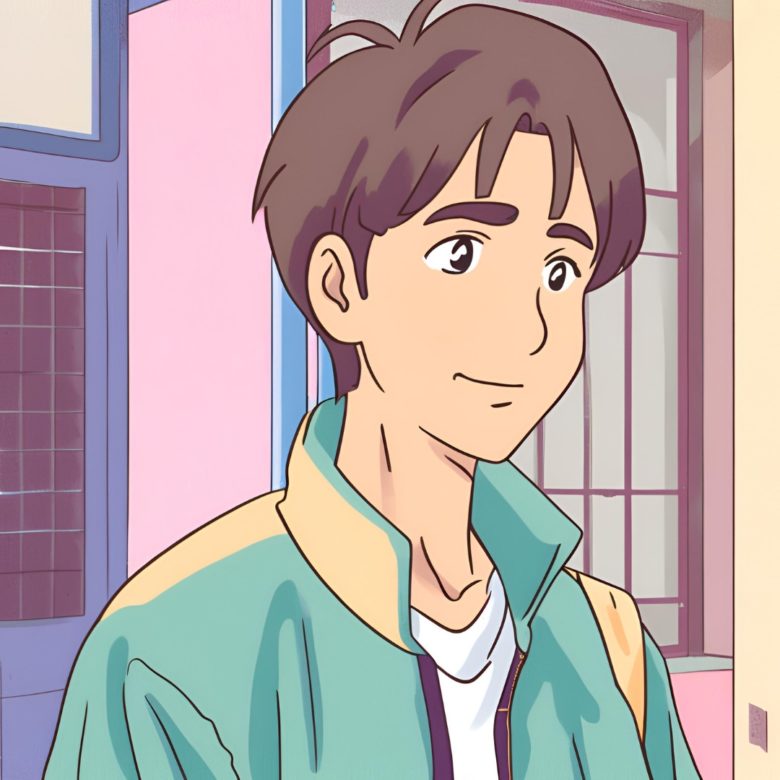竹やぶの薄暗い雰囲気の中、奇怪なオーラをバシバシと放つのがこの「酒船石」だ!!
石には魔法陣のような模様が刻まれており、明らかに何らかの意図をもって加工された石に見えるが実はその用途は詳しくわかっていない
どのような場所なのか写真と共にお伝えします
酒船石までの道のり
酒船石は小高い丘の竹やぶの中に位置しています。夏の訪問ということもあってか、虫が沢山いました
虫を手で払い退けながら進む。虫除けグッズを持ってこれば良かった・・・

しばらくすると、石垣が復元されたエリアにたどり着きます。これは平成4年の調査で発見された石垣の復元。素人目にはその凄さがわかりませんが、この遺構が『日本書紀』で登場する遺跡の記述に一致する可能性があり大変重要な発見で学術的価値がとても高い場所。
ただ、ほんとうにその凄さは感じられない。言っちゃ悪いが、レンガの塀みたいな復元です

酒船石の特徴
先ほどの石垣から歩いて数分で酒船石に到着。思ったよりでかい!
石の上部に魔法陣のような不思議な模様が描かれている。どういう目的で作成されたものなのだろうか??


石を観察すると、水の流れを想定した窪みや溝があることがわかります

両側面を見るといくつものくさびが打ち込まれた形跡がある。このくさびは石を切り出したり加工したりする時に打ち込まれる技術だ。案内板によると近世に元々あった石を誰かが加工し、持ち出した形跡だという
ということは、本来の形は今よりも、もっと大きな物だったと予想できます


古代庭園施設の可能性大
この酒船石の謎については江戸時代の頃から様々な説が唱えられています。
紹介すると、江戸時代の国学者である本居宣長の『菅笠日記』には「むかしの長老の酒ぶね」と現地の伝承を書き留めている。以上から、酒造りに使ったということから「酒船石」と呼ばれるようになったという説である
奈良女子大学学術情報センター『菅笠日記』(1772年)https://www.nara-wu.ac.jp/aic/gdb/nwugdb/edokiko/k017/
ただその後の近世後半に刊行された『西国三十三所名所絵図』には「酒槽に来由いぶかし」(酒造りに使っていたという由来は違うのでは?)と記載されています
早稲田大学図書館古典籍総合データベース『西国三十三所名所図会. 巻之1-8』(1853年)https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko30/bunko30_e0228/index.html
昔から様々な考察がなされてきたんですねえ。また、面白い説で漫画家の手塚治虫『三つ目がとおる』の主人公は、人を奴隷化状態にする薬の調合台と紹介しています
ただ、先ほどの平成で発見された石垣の存在や酒船石が位置する丘から降りた先で当時、水を引いたと見られる亀形石造物の発見があったことから、現在は古代遺跡(宮殿?)の庭園の施設ではないかという説を有力視する学者もいます

しかし、この亀形石造物と酒船石の関連性を否定する説もあり、よくわからない状態になっているそうだ
詳しくはこちら
日本経済新聞 「石と水の都、面影が凝縮 「謎」の遺物 酒船石(時の回廊)」https://www.nikkei.com/article/DGXNASHC03023_U4A700C1AA1P00/
明らかに人の手が加わったもので不思議な形をしているのに、
その用途がよくわかっていないなんてロマンがありますね
アクセス
住所:〒634-0111 奈良県高市郡明日香村岡
駐車場:なし
ただ近隣の奈良県立万葉文化館には有り
営業時間:なし
まとめ
摩訶不思議な模様が描かれた
古の遺物「酒船石」
実際に生で見ると、想像以上に大きく不思議なオーラを放っていました
近隣には、鬼の俎や猿石等酒船石と同様にミステリアスで見たことのない古代の遺物を点在しています
是非あわせて訪問してみてはどうでしょうか!



最後までご覧いただき、ありがとうございました!